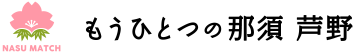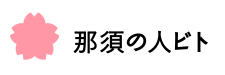長い芦野の歴史において、暮らしと共に寄り添ってきた芦野石。那須の気候、風土に育まれた素材は、移りゆく時代のなかでも変わらず人々に愛されてきました。今回、芦野石の振興会事務局がある株式会社白井石材の代表取締役、白井伸雄さんにインタビューをさせていただきました。芦野石の歴史の話から、建築家の隈研吾さんとの出会いと「石の美術館 STONE PLAZA」の建築に至る経緯。さらに2020年のオリンピックに向けて、新国立劇場の設計を手掛け注目を集める、隈さんと芦野石との関わりなど、お話しは多岐に渡りました。
芦野石が使われたきた芦野のあゆみ
——まず最初に芦野石の歴史についてお聞かせください
もともと芦野は石が露出した地形をしていたので、古くから採石されてきた歴史をもっているんですね。だから芦野石が使われている場所をみていくと、芦野の歴史が分かってきます。神社の鳥居やこの地を統治してきた歴代の芦野氏が祀られている旧墳墓も、建中寺にある新墳墓も芦野石が使われています。
江戸時代には芦野石を使ってお地蔵さんが多く作られました。昔疫病が流行った時代があり、子どもがたくさん亡くなったようです。それで地域に疫病が入って来ないように、芦野宿の入口にお地蔵さんが作られたんだと思います。

そのように芦野の人々の暮らしと密接に芦野石は使われてきましたが、家の土台に使う石など産業として使われるようになったのは、今から100年くらい前からですね。当時は採石の盛んな西日本から技術者が関東に来たみたいです。芦野のほかにも石の取れる福島県白河市や茨城県稲田市も100年以上の歴史があるんですが、香川県の小豆島から技術者が来て、産業としての採石が始まったそうです。石切り場から採石された石は、明治の近代化に合わせて誕生した鉄道が運搬に使われました。
さらに大正時代に起きた関東大震災のときには、鉄道や石垣、建材などに使われる石が復興に向けた需要として増えたそうです。
その後、昭和40年代から50年代にかけて、芦野の石切り場は20か所くらいにまで増え、採石場で働いている人は、最盛期で400人以上いたんです。
そのような景気が平成に入って数年までは続きましたが、バブル崩壊とともに海外からの安い石材が日本に入ってくるようになり、この業界でも倒産する会社が相次ぐ大変な時代を迎えました。

現在弊社を含めて8社が芦野石振興会に加盟しており、石材業を続けています。主に墓石や建築石材として使われていますが、那須町の主要施設としては「那須高原ビジターセンター」や「東山道伊王野道の駅」「那須町観光協会」「ゆめプラザ那須」などの施設の内外壁や敷石に使われています。芦野では「石の美術館 STONE PLAZA」「那須歴史探訪館」に使われています。芦野石はしっかりとした強度がありながら加工もしやすく、自然の景観になじむ風合いをしていますから、エクステリアの用途に適していると思います。

芦野石が使用された那須歴史探訪館のファサード
芦野の職人が4年の歳月をかけ、石蔵をリノベーション
——芦野に「石の美術館 STONE PLAZA」が完成したのが、2000年だそうですが
正式なオープンは2001年の1月からですね。1990年にもともと農協の建物だったものを譲り受けて、94年には社内で「ストーンプラザプロジェクト」という名前で動き出していました。石材会社なので石を作ることは得意ですが、設計はきちんと設計士さんにお願いしたいと思い、知人の紹介で隈研吾さんにご相談をしました。
当時の隈さんは建築家としてはまだ若手でしたが、私は最初引き受けてくれないんじゃないかと思っていました。
というのも、ストーンプラザの建物はすでにあるので、一から設計するわけじゃない。既存の建物を再生するということにやりがいを感じてもらえるのか分からなかったんです。
ありがたいことに、結果として引き受けていただいたんですが、隈さんは何より芦野の景観を気に入ったそうなんですよね。御殿山や町並み、田園風景。どこにでもありそうな田舎なんですが、私は芦野にどこか不思議な雰囲気があると思っているんです。隈さんもそれを感じたのかもしれません。

石の美術館 STONE PLAZA
——「石の美術館 STONE PLAZA」という名前にした理由はなんですか
最初から美術館にする計画ではなく、会社のショールームにしようという案もあったんです。ただ隈さんが石の美術館という名前と目的で使うのはどうでしょうと言ったんです。それで石という素材本来の魅力を伝える美術館として「石の美術館 STONE PLAZA」という名前に決まりました。
もともと農協の倉庫だったので、石の建物のほかに鉄骨の建物がぎっしりと残っていたんです。だからまずはそれを取り払って石の建物だけにして、隈さんに見てもらいました。そうしたらその段階で新たなイメージが生まれたようで「図面を描き直すから、あと半年時間が欲しい」と言われまして(笑)
そして最終的にルーバー※や水面、桟橋で人が渡れるようになっている、現在のストーンプラザの基本的な形になったんですね。しかしその基本設計をもとに96年に着工しましたが、実際に完成するまでに4年もかかってしまいました。ルーバーは薄く切った石を積み重ねていきますが、これが本当に大変で(笑)工場で切った石をトラックでたくさん現場に運んでも、いざ積み上げてみると少しの量にしかならないんです。工場の職人も大変だったと思いますが、根気強くやってくれましてね(笑)バブルが弾けたあとの大変な時期と重なっていたこともあり、とにかく完成させようとみんな必死でした。隈さんも一体いつになったらできるんだろうと思ったみたいで(笑)
※ルーバー:羽板という細長い板を、隙間を空けて平行に組んだもの。柵や塀に使うと、視界や光などを意図的に遮断したり透過したりする効果が生まれる。隈研吾さんの建築物にもよく使用されている。

薄く切った石を積み上げたルーバー
隈研吾さんが設計した「石の美術館 STONE PLAZA」が世界を席巻
——実際完成したときのお気持ちはどうでしたか
半年待ってくれと言われて設計された水面の場所に水が張られたとき、隈さんのイメージがはっきりと目の前に現れた感じがしましたね。「なるほど、こうなるのか」と。
そして2001年にいよいよオープンすると、海外からのお客さんがたくさん見に来てくれましてね。数年間は海外からの団体や大学の研修の方が多かったです。隈さんの関係者の方もいっぱい訪れましたね。
芦野の石職人が苦労してつくった薄くスライスした石のルーバーが、見る者に軽やかな印象を与えると評価されました。そして同じ年にイタリアで開催された国際的な石の展示会「ベローナフェア」で、日本の石の建築物としては初めて「国際石材建築大賞」を受賞しました。おそらくストーンプラザに来た海外のお客さんの中にエントリーに関わった人がいたようですが、誰なのかよく判っていないんです(笑)
9月に授賞式がイタリアで行われ、そこから2年間、世界中の建築系の有名大学とか施設にストーンプラザが受賞作品として巡回展示されました。そこで隈さんが講演に呼ばれてスピーチをしたと聞いています。だから結構、芦野石とストーンプラザのアピールにはなったと思いますね。現在でも国内でこの賞をいただいたのは、ストーンプラザだけです。

石蔵ギャラリー
——栃木県内には、隈さんが設計された施設が点在しています
ストーンプラザの設計がはじまった2年くらい後に、那珂川町で安藤広重の美術館の建設計画があるのを知りまして。隈さんに「コンペに出してみてはいかがですか」と言ったんです。そうしたら見事、隈さんが設計することになりました。
さらにその後、栃木県のまちづくり事業として那須町が芦野に「那須歴史探訪館」を建設する計画があがり、隈さんが設計することになったんです。一番最初に計画が始まったのはストーンプラザですが、完成は「那珂川町馬頭広重美術館」が一番早く、ストーンプラザが最後でしたね。早くできないかなーと思いながら(笑)栃木県には隈さんの設計した建物が多いし、芦野に2つもあるのは誇れることです。広重美術館と歴史探訪館と石の美術館は隈建築の3部作として回る方が多いので、以前はよく3施設のガイド役をやりました。
——隈さんが新国立競技場の設計を手掛けました。今後いいきっかけになればと思います
そうですね。最近芦野石が住宅など建築に多く使われるようになったのは「石の美術館 STONE PLAZA」がひとつのきっかけになったと思います。隈さんが最近設計された建築物にも芦野石が使われていて、つながりを持ち続けています。2020年のオリンピックイヤーに向けて、また多くの方にストーンプラザを訪れていただきたいです。そして隈さんがそうであったように、ストーンプラザや芦野石をきっかけとして、芦野という町の魅力を感じてほしいと思います。